誰もが憧れるテンバガー。
Twitterへの何気ない投稿が意外にも反響がありましたので、ブログでも記事としてまとめておくことにします。
質を伴った拡大が望ましい。
1年以内にテンバガーに達してしまうような銘柄群を見ていると、目に見える「変化」とそこからもたらされる「思惑」の相乗効果による部分がとてつもなく大きいと感じられます。
Tweetでも書いた通り、そこには「ああ、買っておけばよかった!」と思えるような、評価されるに相応しい事業の質を伴ったものは全然見当たりませんでした。
私は「オポチュニティ(機会)」をひたすら貪欲に追い求める企業ではなく、
自らの強みを活かし「クオリティ(質)」を掘り下げていく企業に投資していきたいと常々思っています。
企業が成長していくにしても、それが質を伴ったものでないと長続きはしませんから。
外食産業を見ているとよく分かります。
繰り返し足を運んでくれるお客さんに向けた絶えざる満足度向上への取り組みをおろそかにし、ひたすら拡大に走った結果、短期間で衰退の道をたどる企業のいかに多いことか。
(テンバガー銘柄の中にも見受けられますね)
それはオポチュニティに目がくらみ、クオリティを疎かにした当然の帰結に思えてなりません。
余談ですが、私は投資手法についてもこれと同様だと感じていて、儲かりそうなオポチュニティに飛び付いて回る前に、自分の手法のクオリティを掘り下げていくことが、長続きするコツではないかと考えています。
テンバガーを阻む障壁。
やはりテンバガーは、質を重視しながら時間をかけてゲットするのが王道だと私は思っています。
しかしながら、現実にはそこまでなかなか我慢できないのが人情。
これにはいくつかの要因が考えられます。
- ポートフォリオの中でのウエイトが高くなりがち問題
その株の値動きが全体に与える影響が大きくなってくると、どうしても日々の株価が気になってくるのは仕方のないことです。 - 華々しい成長がオーバーバリューを引き起こしがち問題
目を引く成長は思惑を呼び、実力以上に評価されてしまう恐れがあります。
そして急成長する事業機会には新規参入がつきもので、質に磨きをかけて参入障壁を築いておかないと、実際にはなかなか永続性を伴う事業にはなりにくいということを考慮しておく必要もあります。
「後々、本来の実力を過大に見積もっていたことに気付いてから対応するのでは遅い」と考えるのは自然なことです。 - 成長の限界を意識しがち問題
株式の評価が高まってくると、この先どれだけ成長余地があるのかということを意識せざるを得なくなります。
特に内需企業の場合、これは避けて通れないものです。
では、これらに上手に対処するにはどうしたら良いのでしょうか。
次回はそのやり方について自分なりに考えてみたいと思います。
(続く)


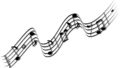
コメント