以前紹介させていただいた「バフェット・クラブの金言」に、以下のような一文があります。
スパークスでは、投資とは「企業の実態価値と価格(株価)との間に生じる差異の裁定機会に主体的に参加すること」と定義しています。
この「主体的に」というのがポイントです。
最終的に「価値」を算出するにしても、その前提(→数式に入力する数値につながっていきます)は人によって全然異なったものであるはず。
「市場の成長性」や、事業の競争優位性や安定性を左右する「経営者の質」「ビジネスモデル」、さらには大元にある「企業文化」といったものまで、様々な要素をどう評価し、そこからどう前提を導くかは、どうやったって属人的なものになります。
当然、人によって全く違った算出結果になる。
つまり、「価値」は一人ひとりの中にある。
だからこそ、受動的であってはならないということですね。
他人が算出した理論株価的なものを利用するにしても、最低でもそのロジックに納得がいってなければ意味がありません。
(それにしたって過去の延長線上で計算せざるを得ないので、限界はあるでしょう。)
導き出された結果としての数字だけで判断していて、何が楽しいのでしょうか。
私が日本株を好むのも、自分で納得しながら前提を置くことができ、またそこに至るまでの情報収集や仮説を組み立てるプロセスが比較的容易で、かつとても楽しいからです。
「主体的に取り組むからこそ、実態価値と価格の差が見えてくる」というスパークスさんの考え方が、経験を重ねるにつれて実感できるようになりました。
こんな構えで投資に取り組む方が、少しでも増えていってくれたらいいなと思っております。
(それがつばめ投資顧問で微力ながらお手伝いさせていただいている理由でもあります。)
↑ ポチっとお願いします。

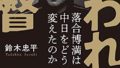

コメント